特例退職被保険者制度
特例退職被保険者制度とは
特例退職被保険者制度は、健康保険組合が行う退職者医療制度です。加入期間中は、現役時代とほとんど同程度のサービスを受けられます。
ただし、平成25年4月以降の男性定年退職者(昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの男性社員)から「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢が順次引き上げられたため、定年退職してすぐに当制度へ加入することができなくなりました。
特例退職被保険者制度(「特退」)の加入可能な年齢は下表のとおりです。
老齢厚生年金受給開始年齢と「特退」加入可能年齢 早見表
| 生年月日 | 老齢厚生年金 (報酬比例部分) 支給開始年齢 |
「特退」 加入可能年齢 |
||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ | 61歳 | 60歳 | 61歳 | 60歳 |
| 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ | ||||
| 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ | 62歳 | 62歳 | ||
| 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれ | ||||
| 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生まれ | 63歳 | 63歳 | ||
| 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ | 61歳 | 61歳 | ||
| 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日生まれ | 64歳 | 64歳 | ||
| 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ | 62歳 | 62歳 | ||
| 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生まれ | 65歳 | 65歳 | ||
| 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ |
63歳 | 63歳 | ||
| 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ | 64歳 | 64歳 | ||
| 昭和41年4月2日~ | 65歳 | 65歳 | ||
加入の条件とは?
- 電通健保に20年以上加入、または40歳以降10年以上加入していること
- 老齢厚生年金を受けているか受給権があること
- 加入可能年齢以上75歳未満であること
- ※在職老齢年金を受けている人はその職場を退職したときに加入条件を満たすことになります。
- ※ご自分で法人組織を設立される場合は、ご相談ください。
- ※加入可能年齢到達時に家族の健康保険被扶養者となっている場合、または国民健康保険に加入している場合は、誕生日からの加入となります。
- ※加入可能年齢到達時に任意継続被保険者となっている場合は、その資格を喪失されてからの加入となります。
資格を喪失するときは?
- 75歳になって後期高齢者医療制度の該当になったとき。あるいは65歳以上で寝たきり等の状態にあり広域連合の障害認定を受けて後期高齢者医療制度の適用を選択されたとき
- 再就職したとき(被保険者になったとき)
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 海外で居住するようになったとき
- 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付が確認できないとき
- 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- ※資格を喪失したときは、忘れずに各証を健康保険組合に返納してください。
- ※一度特例退職被保険者制度に加入したあとは、保険料が高いなどの理由で国民健康保険に移ることはできません。
- ※75歳未満で再就職先を退職した人は再びこの制度に加入することができます。
保険給付は?
在職中と変わりませんが、傷病手当金、傷病手当金付加金は受けられません。
保険料は?
特例退職被保険者の保険料額は、会社負担がなく全額個人負担となります。標準報酬月額は32万円に設定しています。負担する保険料は以下のとおりで、全員定額です。
| 一般保険料 | 介護保険料 注1 | |
|---|---|---|
| 保険料率 | 83.5/1000 | 19.0/1000 |
| 負担額 | 26,720円 | 6,080円 |
- 注1:介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者が納付します。
- ※保険料の前納制度の活用を!
特例退職被保険者の方々には保険料の一定期間の前納制度があります。この場合は、複利現価法によって割り引きされます。
高齢受給者証とは
70歳から74歳までの被保険者並びに被扶養者の方(以下、「高齢受給者」という)には、医療費の一部負担金の割合が2割又は3割と記載された「健康保険高齢受給者証」を交付しています。
保険医療機関等での受診の際に、保険証もしくは資格確認書と併せてご提示してください。
(高齢受給者証のご利用は70歳の誕生月の翌月1日より、誕生日が1日の方は誕生月からとなります。)
一部負担金の割合
新たに交付される高齢受給者証について
70歳以上の特例退職被保険者の方は、標準報酬月額が32万円(現役並み所得者)とされているため、一部負担金の割合は原則として3割負担となります。
ただし、年間収入が一定の基準額(基準収入額)に満たない場合は、以下の「健康保険基準収入額適用申請書」により、電通健保に対して基準収入額の適用申請を行い、認められれば2割負担となります。
- ※「基準収入額」は、単身者は383万円、70歳以上の被扶養者を有する場合は520万円です。
- ※以下の「負担割合の判定について」をご参照ください。
年間収入が基準収入額に満たない場合でも、基準収入額の適用申請を行わない場合は、3割負担となりますのでご注意ください。
- ※電通健保における基準収入額の適用申請の取扱いについては、以下の「特例退職被保険者に対する高齢受給者証の交付について」をご参照ください。
特例退職被保険者に対する高齢受給者証の交付について
基準収入額の適用申請について
電通健保では、高齢受給者証を交付する前に、高齢受給者となる方に対して基準収入額の適用申請について、ご案内いたします。
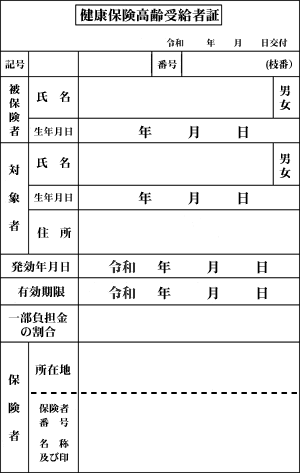
負担割合の判定について
高齢受給者のうち、現役並み所得者で医療費自己負担割合が3割の方は、収入が基準額未満であると認められる場合、申請により自己負担割合が2割になります。
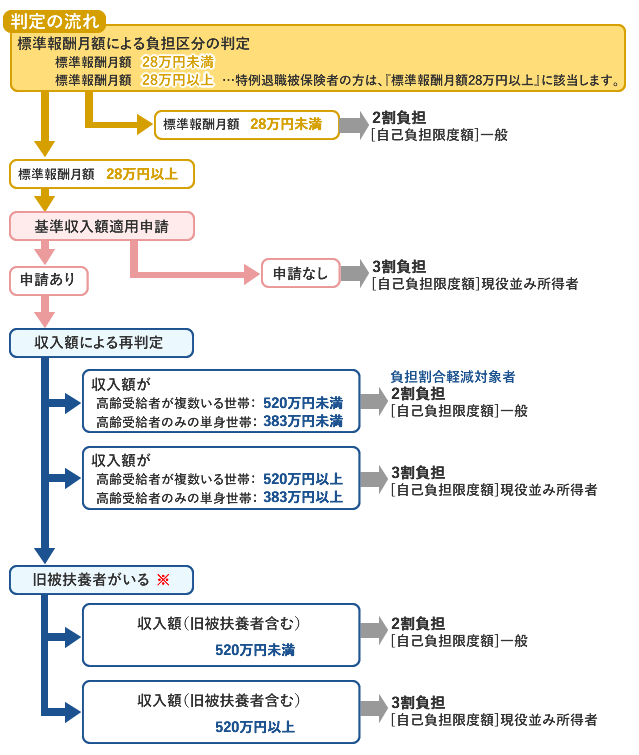
- ※「旧被扶養者」とは、後期高齢者医療制度の被保険者等に該当したことにより、電通健保の被扶養者(家族)から外れた方を指します(扶養をはずれたあと、5年を経過する月までの間に限る)。
毎年の高齢受給者証の更新(負担割合の判定)について
一部負担金の割合が2割又は3割の高齢受給者証を交付されている方は、前年の年間収入額を確認して負担割合を判定するため、毎年9月1日に、高齢受給者証の更新を行います。
更新については、事前に電通健保からご案内いたします。
電通健康保険組合では、毎年の高齢受給者証の更新に関する負担割合を判定する業務(定期判定)を「(株)オークス」へ委託しています。(株)オークスから書類が届いた場合は、すみやかに開封のうえ、提出が必要な方は書類の提出をお願いします。